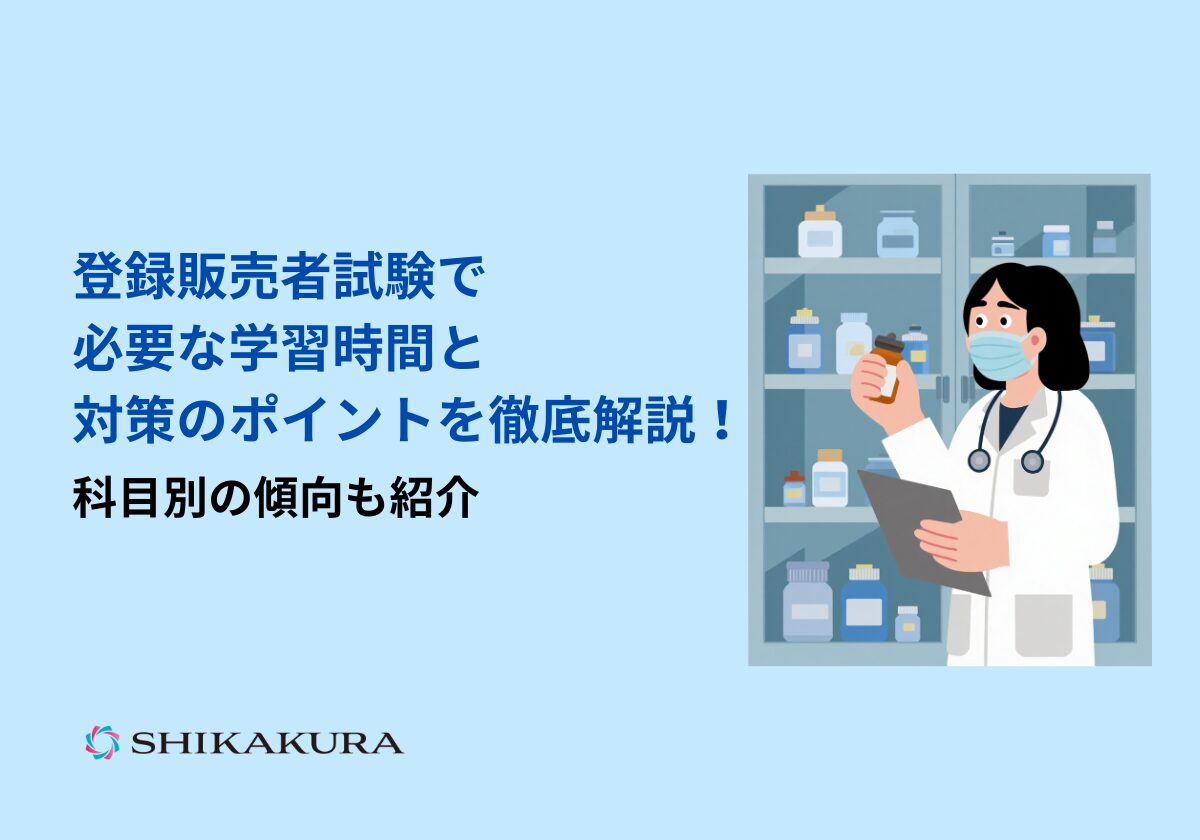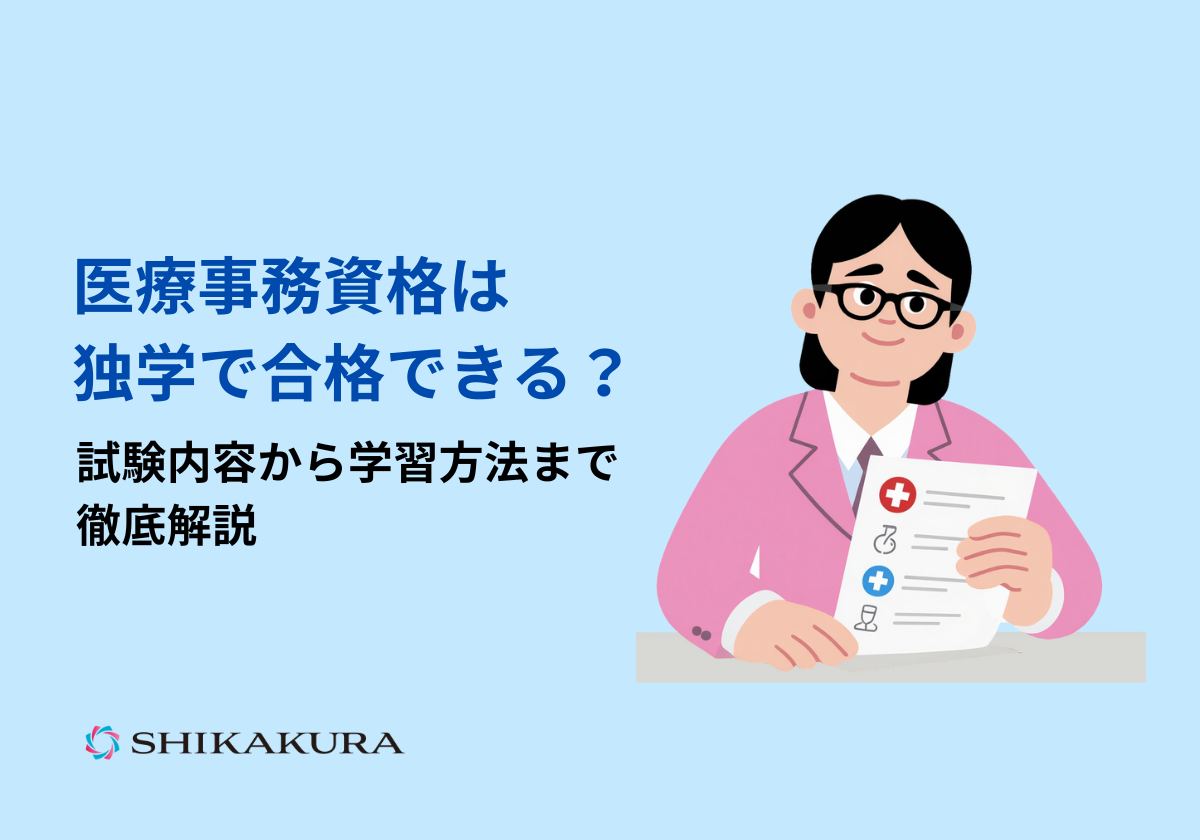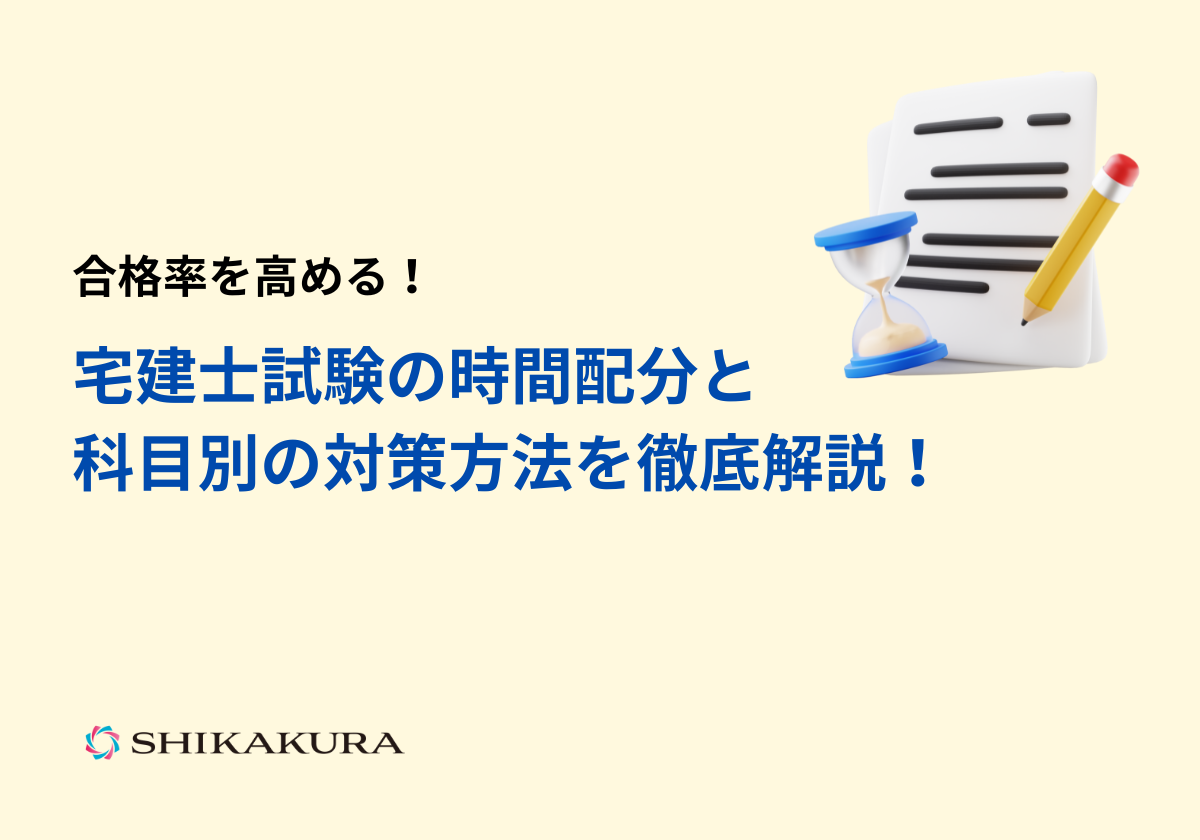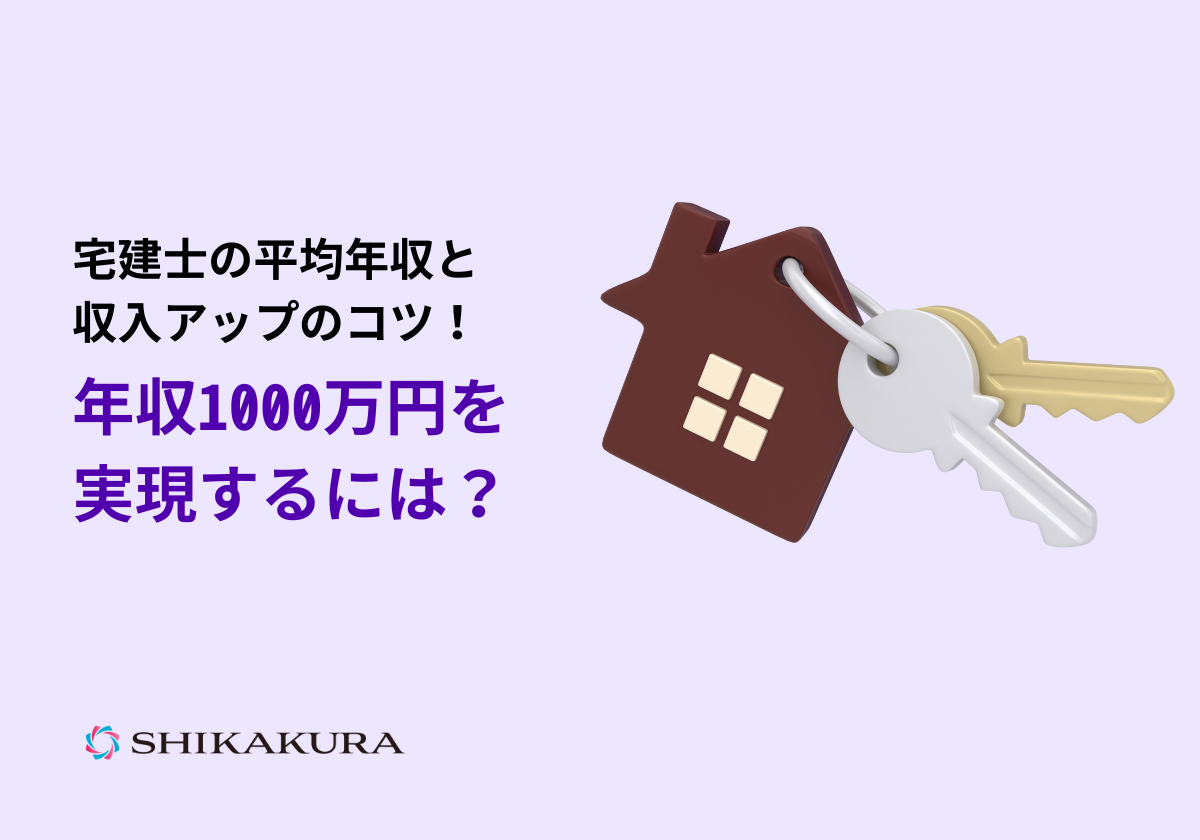公開:2025.8.28 更新:2025.9.10
公開:2025.8.28
宅建の合格率は低い?本当の難易度と合格を掴む勉強法を徹底解説

「宅建に興味があるけど、合格率が15%前後と聞いて、自分には無理かも…」と不安になっていませんか?確かに数字だけを見ると、宅建は難関資格のように思えるかもしれません。
しかし、その数字の裏側にある「本当の難易度」を知らずに諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。
この記事では、宅建の合格率が低いと言われる理由から、他の資格との客観的な難易度比較、そして合格を掴むための具体的な勉強法まで、余すところなく解説します。読み終える頃には、宅建合格への明確な道筋が見えているはずです。
目次
宅建試験の合格率と合格ラインの推移
まずはじめに、気になる宅建試験の合格率や合格ラインのデータをみていきましょう。数字を見ることで、試験の全体像を客観的に把握できます。
過去10年間の合格率・受験者数・合格者数の推移
宅建試験の合格率は、例年15%~17%台で推移しています。これは、100人受けたら15人程度しか合格できない計算になり、数字だけ見れば「低い」と感じるのも無理はありません。
以下に、過去10年間のデータをまとめました。
| 実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格ライン |
| 令和5年 | 289,096人 | 233,276人 | 40,025人 | 17.20% | 36点 |
| 令和4年 | 283,857人 | 226,048人 | 38,525人 | 17.00% | 36点 |
| 令和3年(12月) | 36,923人 | 24,965人 | 3,892人 | 15.60% | 34点 |
| 令和3年(10月) | 256,704人 | 209,749人 | 37,579人 | 17.90% | 34点 |
| 令和2年(12月) | 55,123人 | 35,261人 | 4,610人 | 13.10% | 36点 |
| 令和2年(10月) | 204,250人 | 168,989人 | 29,728人 | 17.60% | 38点 |
| 令和元年 | 273,300人 | 220,797人 | 37,481人 | 17.00% | 35点 |
| 平成30年 | 265,444人 | 213,993人 | 33,360人 | 15.60% | 37点 |
| 平成29年 | 258,511人 | 209,354人 | 32,644人 | 15.60% | 35点 |
| 平成28年 | 245,742人 | 198,463人 | 30,589人 | 15.40% | 35点 |
| 平成27年 | 244,118人 | 194,926人 | 30,028人 | 15.40% | 31点 |
| 平成26年 | 238,620人 | 192,029人 | 33,670人 | 17.50% | 32点 |
※試験実施機関の公表データより作成
※令和2年度、3年度はコロナ禍の影響で試験が2回実施されました。
この表から、毎年20万人以上が受験する非常に人気の高い資格であることがわかります。
合格ライン(合格基準点)は毎年変動する
宅建試験で注意すべき点は、合格ライン(合格に必要な最低点)が毎年変わることです。試験は全部で50問あり、1問1点で採点されます。
「〇〇点取れば必ず合格!」という絶対的な基準はなく、その年の受験者全体の成績によって合格ラインが調整されます。これを相対評価といいます。
過去10年を見ると、合格ラインは31点~38点の間で変動しています。多くの受験生が高得点を取った年は合格ラインが上がり、平均点が低い年は合格ラインが下がる仕組みです。そのため、周りの受験生よりも高い点数を取ることが求められます。
宅建の合格率が低いと言われる3つの理由
合格率15%という数字には、実はカラクリがあります。なぜ宅建の合格率が低く見えるのか、その主な理由を3つ解説します。
理由①:受験資格がなく「記念受験」も多いから
宅建試験には、年齢・学歴・国籍などの受験資格が一切ありません。誰でもチャレンジできる手軽さから、十分な勉強をせずに「試しに受けてみよう」という層、いわゆる「記念受験」の人が多く含まれます。
不動産会社が社員に一括で申し込みをし、ほとんど勉強せずに受けるケースも少なくありません。
こうした本気度の高くない受験者が分母に含まれるため、見かけ上の合格率が低くなっています。しっかりと対策をした受験者に絞れば、実際の合格率はもっと高いと言えるでしょう。
理由②:合格者数を調整する「相対評価」だから
先ほども触れたように、宅建試験は「相対評価」です。これは「上位およそ15%前後を合格させる」という方針であらかじめ合格者の割合が決まっていることを意味します。
もし、試験問題が非常に簡単で、多くの人が満点を取ったとしても、全員が合格するわけではありません。逆に、どんなに難しい年でも、必ず一定数の合格者が出ます。
つまり、周りとの競争に勝つ必要があるため、誰でも簡単に合格できる試験ではないのです。これが、合格率が一定の低い水準で安定している大きな理由です。
理由③:出題範囲が広く十分な対策が必要だから
宅建試験は、大きく分けて4つの分野から出題されます。
権利関係(民法など):契約や相続といった法律のルール
宅建業法:不動産取引の専門的な法律
法令上の制限:街づくりのルール(都市計画法など)
税・その他:不動産に関する税金や統計情報
このように、法律から税金まで出題範囲が非常に広いため、合格するにはまんべんなく、かつ計画的な学習が不可欠です。付け焼き刃の知識では太刀打ちできず、十分な勉強時間を確保して対策した人だけが合格を掴める試験と言えます。
宅建の本当の難易度は?他の人気資格と比較
「合格率のカラクリはわかったけど、結局どれくらい難しいの?」と感じる方も多いでしょう。ここでは、宅建の難易度を他の資格と比較して、客観的な立ち位置をみていきます。
偏差値で見る宅建の難易度の位置づけ
資格の難易度を偏差値で表すと、宅建の偏差値は「57」前後と言われています。
これは、大学入試に例えると日本大学や東洋大学、駒澤大学、専修大学(日東駒専)レベルに相当し、決して簡単ではありませんが、超難関というわけでもありません。
つまり、正しい方法でコツコツと努力を積み重ねれば、誰でも十分に合格を狙えるレベルの資格である、と考えることができます。決して、才能や特別な能力が必要な試験ではないのです。
他の不動産・法律系資格との難易度比較
宅建と関連性の高い、他の人気資格と難易度を比べてみましょう。
マンション管理士・管理業務主任者との比較
マンション管理に関する国家資格である「マンション管理士(マン管)」と「管理業務主任者(管業)」。宅建と試験範囲が重なる部分も多い資格です。
難易度:マンション管理士 > 宅建 > 管理業務主任者
特徴:マン管は合格率8%前後の難関資格です。一方、管業は合格率20%前後で、宅建より少し易しいレベルとされています。宅建合格後にステップアップとしてこれらを目指す人も多いです。
FP(ファイナンシャルプランナー)との比較
お金の専門家であるFP。特にFP2級は人気の資格です。
難易度:宅建 > FP2級
特徴:FP2級の合格率は40%前後(学科試験)と宅建より高めです。ただし、出題範囲が異なるため一概には比較できません。金融や保険に興味があるならFP、不動産に興味があるなら宅建がおすすめです。
行政書士との比較
法律系の国家資格として人気の行政書士。
難易度:行政書士 >> 宅建
特徴:行政書士の合格率は10%前後で、宅建よりも低くなっています。記述式の問題があるなど、より深い法律知識が求められるため、宅建よりもかなり難易度は高いと言えるでしょう。
宅建合格を勝ち取るための試験攻略法
宅建は、やみくもに勉強しても合格は難しい試験です。ここでは、合格の可能性をぐっと高めるための具体的な攻略法をお伝えします。
合格に必要な勉強時間は300~400時間が目安
宅建合格に必要な勉強時間は、一般的に300時間~400時間と言われています。法律の知識がまったくない初学者の場合、これくらいの時間はみておくと安心です。
仮に350時間の勉強を目標にするなら以下の勉強時間が必要です。
半年(6ヶ月)で合格を目指す場合:1日あたり約2時間
3ヶ月で合格を目指す場合:1日あたり約4時間
の勉強が必要になります。自分のライフスタイルに合わせて、無理のない学習計画を立てることが大切です。
科目別の目標点と学習の優先順位
宅建は全50問ですが、科目ごとに配点が異なります。すべての分野を完璧にするのではなく、点を取りやすい分野で確実に得点し、難しい分野では深追いしないというメリハリが重要です。
宅建業法|最優先で満点を目指す(目標:18点/20問)
宅建業法は、20問と最も配点が高い最重要科目です。出題範囲が比較的狭く、過去問の繰り返しで得点しやすいため、最優先で取り組み、満点を目指しましょう。ここでの失点は致命傷になりかねません。
権利関係(民法など)|深追いしすぎず基本を押さえる(目標:8点/14問)
民法を中心とする権利関係は、14問出題されます。範囲が膨大で、難解な問題も多いため、深追いは禁物です。誰もが解けるような基本的な問題を確実に正解し、半分ちょっと(8点程度)取れれば十分と割り切りましょう。
法令上の制限|暗記が得点に繋がりやすい(目標:6点/8問)
都市計画法や建築基準法など、聞き慣れない法律が多く登場しますが、内容は暗記が中心です。努力がそのまま点数に結びつきやすいため、数字や用語を正確に覚えることを意識しましょう。得点源にしたい分野です。
税・その他|コストパフォーマンスを意識する(目標:5点/8問)
税金や地価公示、統計情報などから8問出題されます。範囲が広い割に配点が少ないため、時間をかけすぎないように注意が必要です。特に、毎年内容が変わる統計問題は、試験直前に詰め込むのが効率的です。
5点のアドバンテージ!登録講習(5問免除)制度とは?
不動産業に従事している方限定ですが、「登録講習」という制度を利用すると、試験問題50問のうち最後の5問が免除されます。
これは、合格ラインが毎年35点前後で争われる宅建試験において、スタート時点で5点のアドバンテージを持っているのと同じことで、絶大な効果があります。合格率も、一般の受験者に比べて10%近く高くなる傾向にあります。
受講には数万円の費用と数日間のスクーリングが必要ですが、対象となる方は利用を強くおすすめします。
あなたに合った学習計画の立て方
自分に合った学習スタイルを見つけることが、挫折せずに合格まで走り抜けるコツです。
いつから始める?学習開始時期ごとのモデルプラン
宅建試験は毎年10月の第3日曜日です。そこから逆算して、いつから勉強を始めるか計画を立てましょう。
1年前~春(4月頃)から始めるプラン
メリット:余裕を持って基礎からじっくり学べる。1日あたりの勉強時間が短くて済む。
ポイント:まずは参考書を1周読み、全体像を掴むことから始めましょう。夏までにインプットを終え、秋からは過去問演習に集中するのが理想です。
夏(6月~7月頃)から始めるプラン
メリット:短期集中で知識が定着しやすい。モチベーションを維持しやすい。
ポイント:インプットとアウトプット(過去問演習)を同時並行で進める必要があります。特に「宅建業法」など得点源となる科目を優先して攻略しましょう。
独学と予備校、どちらを選ぶべき?メリット・デメリットを比較
学習方法は大きく分けて「独学」と「予備校(通信・通学)」があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方を選びましょう。
独学が向いている人の特徴
- 費用を抑えたい人
- 自分で学習スケジュールを管理できる人
- マイペースに勉強を進めたい人
市販の教材費(1万円程度)だけで済むのが最大のメリットです。しかし、強い意志がないと途中で挫折しやすいというデメリットもあります。
予備校(通信・通学)が向いている人の特徴
- 効率的に合格を目指したい人
- 何から手をつけていいかわからない初学者の人
- 一人だと勉強が続かない人
費用はかかりますが、合格のノウハウが詰まったカリキュラムで学べるため、最短ルートで合格を目指せます。特に、スマホで学べる通信講座は、忙しい社会人や学生に人気です。
モチベーションアップ!宅建に合格するメリット
つらい勉強を乗り越えた先には、たくさんのメリットが待っています。合格後の輝かしい未来を想像することが、学習のモチベーションに繋がります。
不動産業界への就職・転職に必須級
不動産会社では、従業員5人につき1人以上の宅建士を設置することが法律で義務付けられています。そのため、宅建資格は不動産業界への就職・転職において、パスポートのような役割を果たします。未経験者でも、資格を持っているだけで採用の可能性が大きく上がります。
キャリアアップと年収向上が期待できる
宅建士にしかできない「独占業務」(重要事項の説明など)があるため、社内でのキャリアアップに直結します。多くの企業で月1万円~5万円程度の資格手当が支給されるため、年収アップも期待できます。責任ある仕事を任され、やりがいも大きくなるでしょう。
私生活(不動産取引など)でも知識が役立つ
宅建で学ぶ法律や税金の知識は、私たちの生活に密接に関わっています。マイホームの購入や賃貸契約、相続といった人生の重要な場面で、専門知識を活かすことができます。不動産取引で不利な契約を結んでしまうリスクを減らせるのは、大きな安心材料です。
まとめ:宅建の合格率は数字に惑わされず、正しい対策で合格を目指そう
今回は、宅建の合格率と本当の難易度、そして具体的な攻略法について解説しました。
最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。
- 宅建の合格率は15%前後だが、「記念受験」が多いため数字以上に難しくはない
- 難易度は偏差値57程度。正しい努力で十分に合格できるレベル
- 合格のカギは「宅建業法」で満点を狙い、科目ごとにメリハリをつけること
- 必要な勉強時間は300~400時間。自分に合った学習計画を立てることが重要
- 合格すれば、就職・転職、年収アップなど大きなメリットがある
合格率という数字だけを見て、「自分には無理だ」と諦める必要はまったくありません。宅建は、しっかりと戦略を立てて対策すれば、誰にでも合格のチャンスがある資格です。
この記事を読んで、ぜひ宅建合格への第一歩を踏み出してください。あなたの挑戦を心から応援しています!

![「資格」と「比較」をするメディア[シカクラ]](https://shikakura-x.com/wp/wp-content/themes/shikakura/dev/public/assets/images/common/text3.svg)











![[タグから記事をさがす]](https://shikakura-x.com/wp/wp-content/themes/shikakura/dev/public/assets/images/common/text_tag_search.svg)