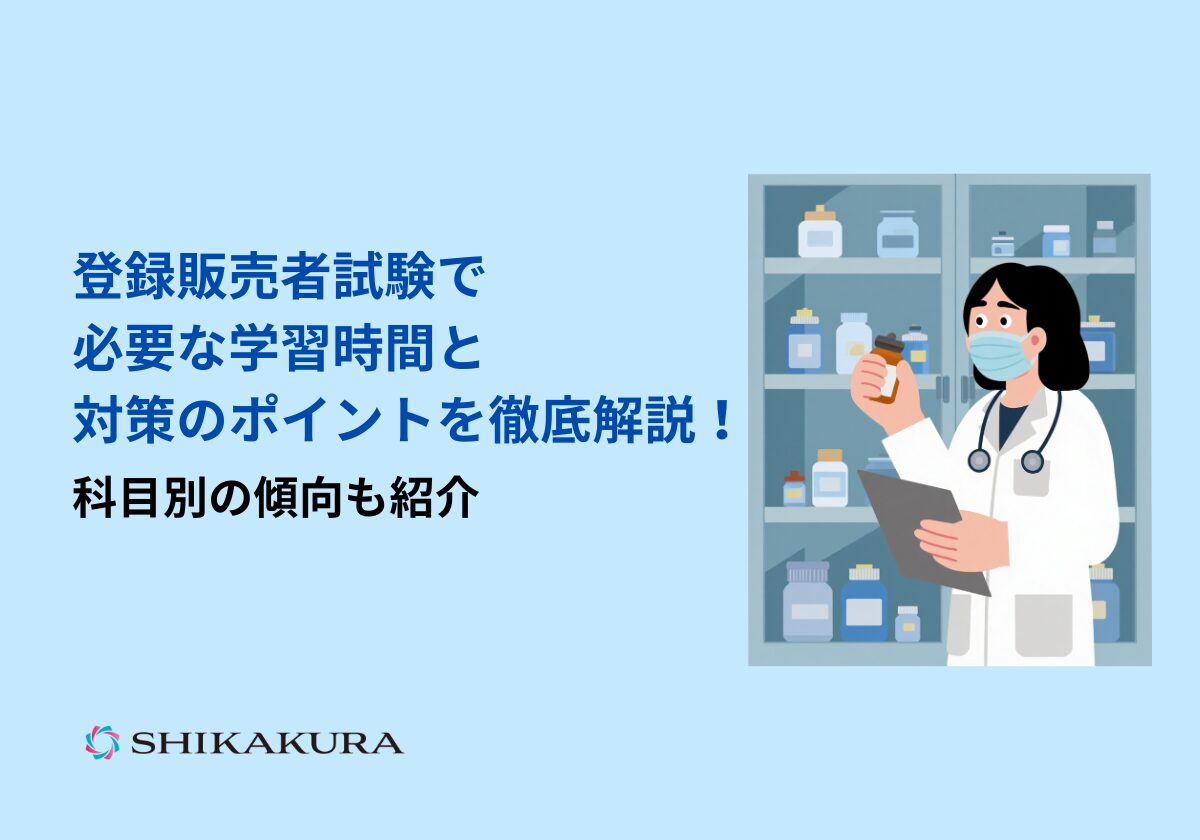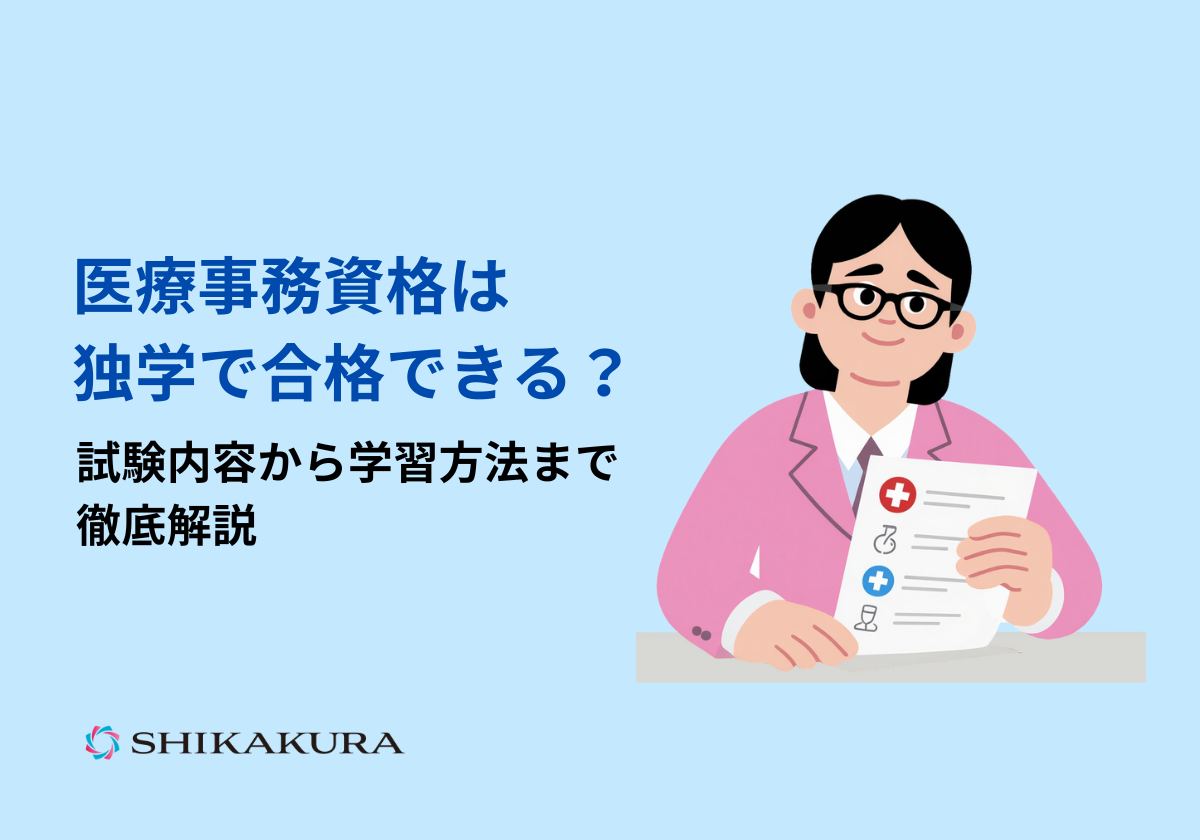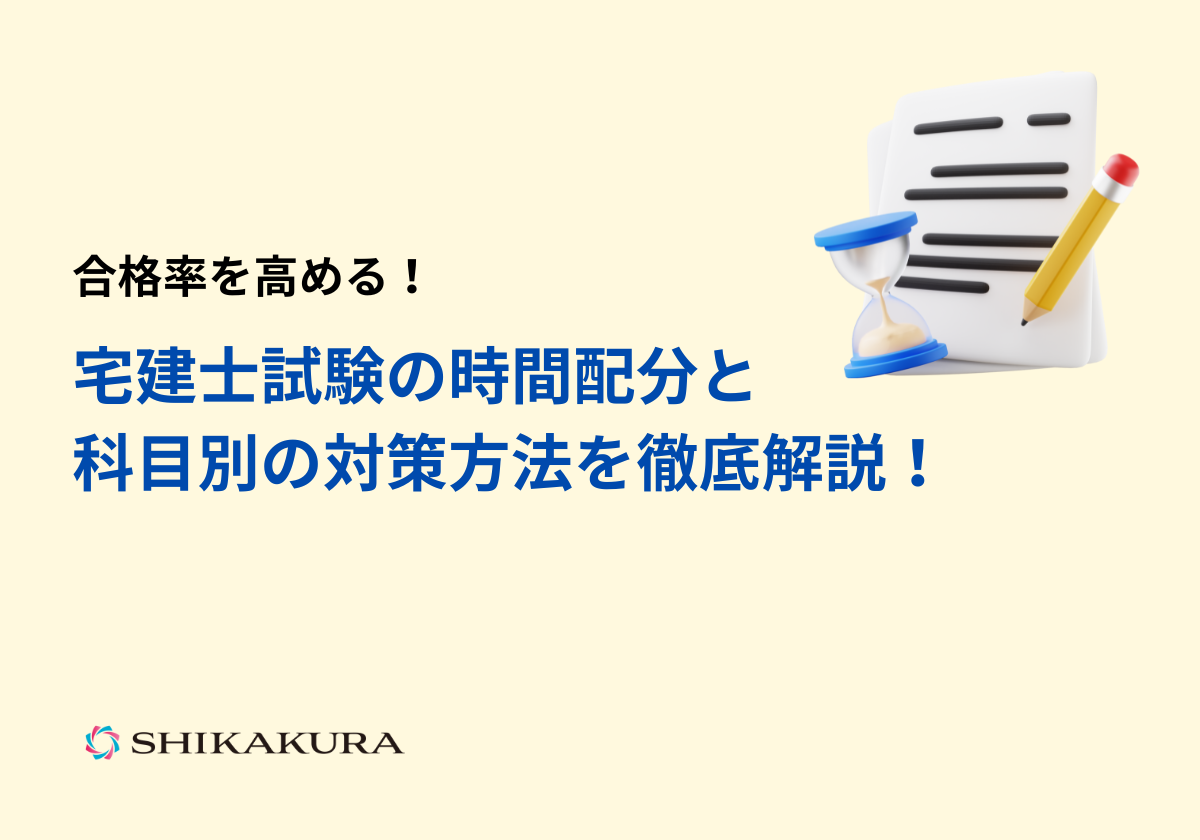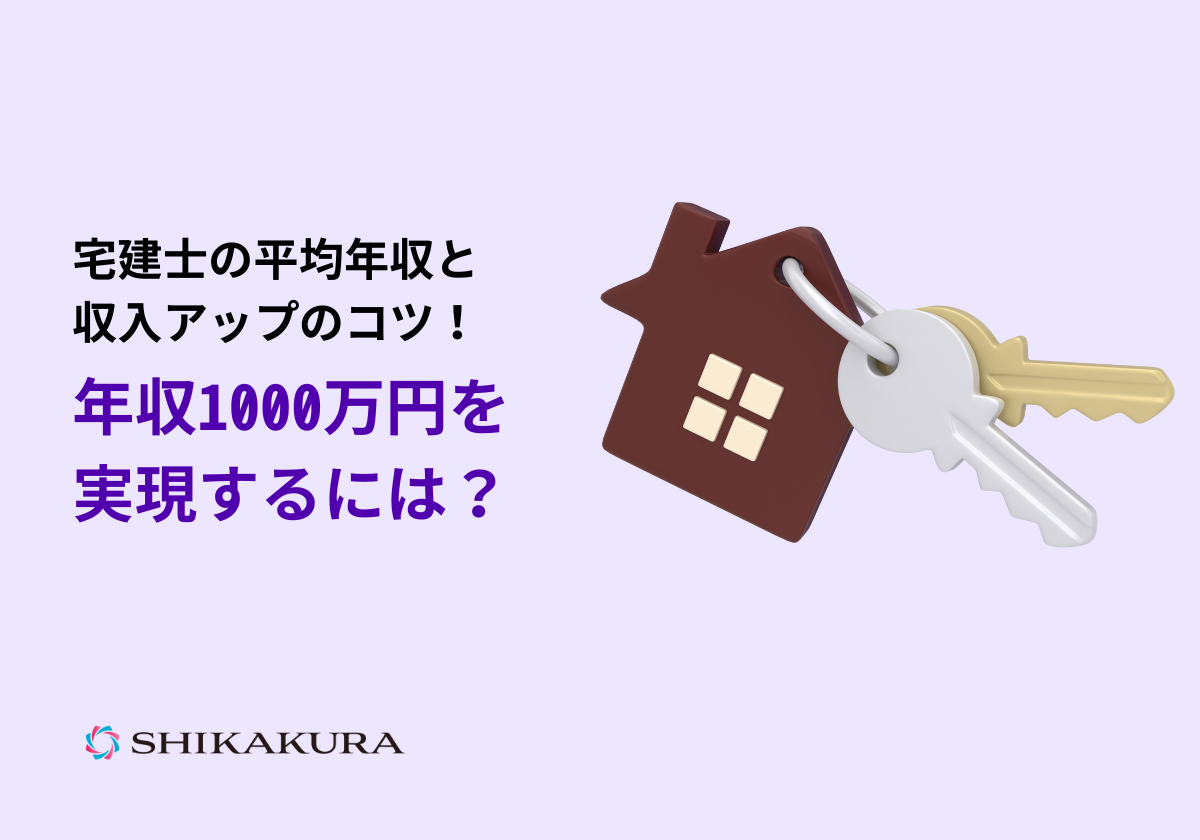【2025年】宅建の試験日は10月19日(日)!申込期間から合格発表までの全スケジュールを徹底解説

2025年(令和7年)に宅建試験の合格を目指すすべての方へ。年に一度の国家資格チャレンジ、その第一歩は正確なスケジュール把握から始まります。
「試験日はいつ?」「申し込みはいつから?」そんなあなたの疑問に、この記事一本で完璧にお答えします。
この記事では、2025年度の宅建試験日をはじめ、申し込み開始から合格発表、さらには資格登録までの全日程を徹底的に解説。この記事を読めば、試験当日まで迷うことなく、安心して勉強に集中できるでしょう。さあ、一緒に合格への道を歩み始めましょう。
目次
2025年(令和7年度)宅建試験の重要日程早わかり表
まずは結論から。
宅地建物取引士(宅建士)の試験は、例年10月の第3日曜日に行われます。令和7年(2025年)の試験日は10月19日(日)です。試験時間は、13時から15時までの2時間で、試験の申し込みは、例年7月1日から7月15日頃までに行われます。
2025年度(令和7年度)宅建試験の全体像を把握できるよう、重要な日程を一覧表にまとめました。忙しい方は、まずこの表で試験となる日付をチェックしてください。
スマホのスケジュール帳に登録しておくと、うっかり忘れる心配がなくなるのでおすすめです。
| 時期 | イベント内容 | 備考 |
| 6月6日(金) | 試験の公式発表(公告) | 試験日、受験料などが正式に決まります。 |
| 7月1日~7月31日 | 受験申し込み期間 | インターネット申込は7月19日(金)までが一般的です。 |
| 8月下旬~ | 試験会場の通知 | ハガキで通知されます。会場の変更は原則できません。 |
| 10月上旬 | 受験票の発送・到着 | 受験票が届かない場合は、必ず問い合わせましょう。 |
| 10月19日(日) | 宅建試験 本番 | 試験時間は13:00~15:00の2時間です。 |
| 11月26日(火) | 合格発表 | 合格基準点や合格率もこの日に発表されます。 |
| 合格後 | 資格登録手続き | 合格しただけでは「宅建士」とは名乗れません。 |
※上記の日程は2025年のスケジュールです。
参照:「一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 宅建試験 | 宅建試験のスケジュール」
https://www.retio.or.jp/exam/schedule/
宅建試験の申し込みから合格までの完全ロードマップ
宅建試験は、申し込んで終わりではありません。合格というゴールまでには、いくつかのステップが存在します。ここでは、試験の発表から合格後の手続きまで、時系列に沿ってあなたが「いつ・何をすべきか」を具体的に解説します。
【6月】試験の公式発表(公告)
毎年6月の第1金曜日に、その年の宅建試験の詳細が官報で公式に発表されます。これを「公告(こうこく)」と呼びます。
この発表で、試験日や受験手数料、申し込み方法といった試験の大枠が決まります。不動産適正取引推進機構(RETIO)のウェブサイトにも情報が掲載されるため、宅建受験生は必ずチェックしましょう。この時期から、試験本番までのカウントダウンが本格的にスタートするといえます。まずは公式サイトをブックマークしておくのがおすすめです。
【7月】受験申し込み手続きの開始
7月に入ると、いよいよ受験の申し込みが始まります。申し込み方法は「インターネット」と「郵送」の2種類です。
注意点として、インターネット申込は郵送よりも期間が短い傾向にあります(例年7月中旬まで)。郵送申込は7月末日まで受け付けていますが、願書(申し込み書類)の取り寄せに時間がかかることも。どちらの方法を選ぶにせよ、締め切り間際はアクセス集中や郵便の遅れが心配です。余裕を持って、7月上旬には手続きを終えるように心がけましょう。
【8月下旬】試験会場の通知
申し込みが無事に完了すると、8月下旬ごろに「試験会場通知」というハガキが届きます。このハガキには、あなたが受験する会場の名称と所在地が記載されています。
ここで大切なのは、試験会場は自分で選べないという点です。お住まいの地域に基づいて自動的に割り振られるため、希望と違う場所になることも。通知が届いたら、すぐに会場の場所と交通アクセスを確認し、当日迷わないように準備しておきましょう。原則として会場の変更はできないので注意してください。
【10月上旬】受験票の到着と最終確認
試験日のおよそ2週間前、10月上旬になると、受験票が郵送で届きます。受験票は、試験会場への入場パスポートのようなものです。絶対に失くさないように大切に保管しましょう。
受験票が届いたら、以下の3点を必ず確認してください。
①氏名や生年月日に間違いはないか
②顔写真が鮮明に印刷されているか
③試験会場が「試験会場通知」のハガキと同じか
もし間違いがあったり、10月中旬を過ぎても受験票が届かない場合は、すぐに試験協力機関へ問い合わせることが重要です。
試験本番
いよいよ、これまでの努力が試される試験本番の日です。2025年の試験日は、10月19日(日)が予定されています。
試験時間は午後1時から午後3時までの2時間です。ただし、試験に関する注意事項の説明があるため、集合時間はもう少し早くなります。遅くとも12時30分までには自分の席に着席している必要があります。当日は公共交通機関の遅延なども考えられますので、時間に余裕をもって会場へ向かいましょう。最後の1分まで諦めず、全力を出し切ってください。
運命の合格発表
長い戦いを終え、緊張の合格発表は11月下旬に行われるのが通例です。2025年は11月26日(火)になっています。
発表日の午前9時30分に、不動産適正取引推進機構のウェブサイトで合格者の受験番号が公開されます。同時に、合格基準点や合格率も発表されるでしょう。自分の番号を見つけたときの喜びは、何ものにも代えがたいものです。合格者には、後日「合格証書」が郵送で届きます。この証書は、次のステップである資格登録に必要となります。
【合格後】資格登録の手続きについて
宅建試験に合格しただけでは、「宅地建物取引士(宅建士)」と名乗ることはできません。宅建士として仕事をするためには、受験した都道府県で「資格登録」を行い、「宅地建物取引士証」の交付を受ける必要があります。
この資格登録には、宅建業での実務経験が2年以上必要です。もし実務経験がない場合は、「登録実務講習」という講習を修了することで、2年以上の実務経験があるとみなされます。合格後も手続きが必要なことを覚えておきましょう。
宅建試験の申し込み方法を徹底解説【インターネット・郵送】
宅建試験の申し込みは、決して難しくありません。しかし、いくつか押さえておくべきポイントがあります。ここでは、申し込み方法ごとの手順や注意点を分かりやすく解説します。
申し込み前に準備するものリスト(顔写真・受験料など)
申し込みをスムーズに進めるために、あらかじめ以下のものを準備しておきましょう。
・顔写真のデータ(インターネット申込の場合)
・無帽、正面、無背景で3ヶ月以内に撮影したもの
・ファイル形式やサイズに指定があるので注意
・証明写真(郵送申込の場合)*1
・パスポート申請用サイズ(縦4.5cm×横3.5cm)
・受験手数料:8,200円(予定)
・インターネット申込:クレジットカードまたはコンビニ決済
・郵送申込:指定の払込用紙で銀行振込
・メールアドレス(インターネット申込の場合)*2
(*1)顔写真は規格が細かく決まっています。規定外の写真は受付不可となり、再提出を求められることも。証明写真機や写真館で「宅建試験用」と伝えるとスムーズです。
(*2)登録や通知の受信に必要です。
・インターネット申込の手順と注意点
PCやスマホから24時間いつでも申し込めるため、近年はインターネット申込が主流です。手順はとてもシンプルです。
①不動産適正取引推進機構のウェブサイトにアクセス
↓
②案内に従い、メールアドレスを登録
↓
③氏名、住所などの個人情報を入力
↓
④顔写真データをアップロード
↓
⑤クレジットカードやコンビニ払いで受験手数料を決済
【注意点】
インターネット申込は、郵送申込よりも締め切りが2週間ほど早い点に注意が必要です。また、申込期間の最終日はアクセスが集中してサイトが重くなることもあります。できるだけ早く手続きを済ませましょう。
・郵送申込の手順と注意点
郵送での申し込みも可能です。インターネット操作が苦手な方でも安心して手続きできます。
①試験案内(願書)を入手する
↓
②願書に必要事項を記入し、証明写真を貼り付ける
↓
③銀行で受験手数料を振り込み、受領証を願書に貼る
↓
④願書を特定記録郵便で郵送する
【注意点】
郵送申込で最も重要なのは、願書の入手です。配布場所に直接取りに行くか、郵送で請求する必要があります。また、郵便局の窓口で「特定記録郵便」で送ることを忘れないでください。普通郵便で送ると受け付けてもらえません。締め切り日の消印まで有効ですが、余裕を持った投函が大切です。
・試験案内(願書)の入手方法と配布場所
郵送申込に必要な「試験案内(願書)」は、7月上旬から各都道府県で配布が開始されます。主な配布場所は以下の通りです。
・都道府県の庁舎(宅建業の担当部署)
・土木事務所など、県の出先機関
・大型書店
配布場所は都道府県によって異なります。事前に各都道府県の宅建業担当部署のウェブサイトで確認するのが確実です。近くに配布場所がない場合は、郵送で取り寄せることもできますが、返信用封筒の準備などが必要になるため、早めに行動しましょう。
これだけは押さえたい!宅建試験の基本情報(試験概要)
ここでは、宅建試験そのものに関する基本的な情報をまとめました。試験のルールを知ることは、合格戦略を立てる上での第一歩です。
受験資格は?誰でもチャレンジ可能
宅建試験の大きな魅力の一つは、受験資格に制限がないことです。年齢、学歴、国籍、実務経験などに関係なく、誰でも受験できます。
実際に、学生から主婦、定年後の方まで、幅広い層の人たちが毎年チャレンジしています。不動産業界を目指す人はもちろん、自身の知識を深めるために受験する人も少なくありません。「法律の勉強は初めて」という方でも、しっかり対策すれば十分に合格が狙える、門戸の開かれた資格といえるでしょう。
・試験形式と出題科目・配点
宅建試験は、全50問、四肢択一式のマークシート形式で行われます。つまり、4つの選択肢の中から最も正しい(または、誤っている)ものを1つ選んで回答する形式です。記述式の問題はありません。
出題科目は大きく分けて4つです。
権利関係(14問):民法や借地借家法など、契約や不動産の権利に関する分野。
宅建業法(20問):宅建業者が守るべきルール。最も配点が高く、得点源にしたい科目。
法令上の制限(8問):都市計画法や建築基準法など、土地の利用に関する制限の分野。
税・その他(8問):不動産に関する税金や、不動産の価格評価など。
・試験時間と当日の流れ
試験時間は、午後1時から午後3時までの2時間(120分)です。ただし、後述する「登録講習」の修了者は、試験時間が10分短縮され、1時間50分となります。
当日の大まかな流れは以下の通りです。
12:30まで:指定された席に着席
12:30~13:00:受験の注意事項説明、問題用紙・解答用紙の配布
13:00~15:00:試験開始~終了
15:00:解答終了。問題用紙と解答用紙が回収される
試験開始から30分が経過するまで、また試験終了前の10分間は、途中退出ができません。トイレは事前に済ませておきましょう。
受験手数料と支払い方法
2025年度の宅建試験の受験手数料は8,200円です。近年、受験手数料は改定されることがあるため、公式発表で必ず確認してください。
支払い方法は、申し込み方法によって異なります。
インターネット申込:クレジットカード決済、またはコンビニエンスストア決済が利用できます。
郵送申込:試験案内に同封されている専用の払込用紙を使って、銀行の窓口で振り込む必要があります。ATMやネットバンキングからの振込は認められていないので注意が必要です。
宅建試験の合格を掴むための基礎知識
ただ試験を受けるだけでなく、「合格する」ために知っておきたい知識があります。合格ラインや勉強時間など、具体的な目標設定に役立つ情報を見ていきましょう。
気になる合格ラインと近年の合格率
宅建試験は、〇点取れば必ず合格、という絶対評価の試験ではありません。毎年合格ラインが変動する「相対評価」の試験です。
近年の合格ラインは、50問中34点~38点の間で推移しています。つまり、7割程度の正解がひとつの目安となります。
また、合格率は毎年15%~17%前後で、簡単な試験ではないことがわかります。約6人に1人しか合格できない難関資格だからこそ、計画的な学習が合格の鍵を握るのです。まずは「50問中40点取る」ことを目標に学習を進めるとよいでしょう。
・合格に必要な勉強時間の目安は?
宅建試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に300時間~400時間といわれています。
もちろん、これはあくまで目安です。法律の学習経験がある方ならもっと短く、全くの初学者であればもう少し時間が必要になるかもしれません。
仮に350時間とすると、1日2時間の勉強を続けた場合、約半年(約175日)かかる計算です。試験が10月にあることを考えると、遅くとも春先(4月頃)には学習をスタートするのが理想的といえます。自分のライフスタイルに合わせて、無理のない学習計画を立てましょう。
注意すべきポイントや法改正について
宅建試験では、その年の4月1日時点で施行されている法律が出題範囲となります。法律は毎年のように改正されるため、古いテキストや過去問だけで勉強していると、間違った知識を覚えてしまう危険性があります。
特に民法や宅建業法は、近年大きな改正がありました。最新の法改正に対応した教材を選ぶことが、合格への最短ルートです。独学で勉強する方は、法改正の情報を自分でキャッチアップする必要があります。予備校や通信講座を利用すると、そうした情報を効率的に得られるというメリットもあります。
・登録講習(5点免除)制度とは?
「登録講習」とは、宅地建物取引業に従事している方を対象とした制度です。この講習を修了すると、本試験の50問のうち、問46から問50までの5問が免除されます。
つまり、45問を解いて採点されることになり、試験時間も10分短縮されます。この5問は比較的マニアックな分野から出題されるため、免除されるメリットは非常に大きいです。
免除対象となる出題分野(問46~50)については、以下の通りです。
・問46:住宅金融支援機構法
・問47:不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
・問48:統計
・問49:土地
・問50:建物
特に「統計」は毎年変わる数値を直前に覚え直す必要があり、学習のタイミングが難しいです。そして、「住宅金融支援機構法」や「景品表示法」は、特定の法律の細かい規定からの出題になるため専門性が高いことから難易度が高く、「土地」「建物」は範囲が広く、対策を立てにくいと感じる受験者が多いです。
ただし、受講するには「宅建業の従業者証明書」を持っていることが条件です。不動産会社にお勤めの方は、自分が対象になるか会社に確認してみることをおすすめします。
宅建の試験日に関するよくある質問(Q&A)
最後に、宅建の試験日や申し込みに関して、多くの方が抱く疑問にQ&A形式でお答えします。不安な点はここで解消しておきましょう。
Q. 宅建試験は年に何回ありますか?
A. 宅建試験は、年に1回のみ実施されます。
毎年10月の第3日曜日に全国一斉に行われるのが原則です。もし不合格だった場合、再チャレンジできるのは翌年になります。年に一度のチャンスを逃さないよう、万全の準備で臨むことが大切です。
(※コロナ禍では10月と12月の2回に分けて実施された年もありましたが、現在は年1回の実施に戻っています。)
Q. 試験当日に遅刻したらどうなりますか?
A. 試験開始後30分までの遅刻であれば、受験が認められます。
ただし、試験時間の延長は一切ありません。つまり、遅刻した分だけ試験時間が短くなるという厳しいペナルティがあります。30分を超えて遅刻した場合は、いかなる理由があっても試験室への入室はできず、受験資格を失います。当日は、何が起きてもいいように、早めの行動を心がけてください。
Q. 過去問は何年分解くのがおすすめですか?
A. 目安として、最低でも直近10年分の過去問を解くことをおすすめします。
過去問は、出題傾向や時間配分を体感するための最高の教材です。ただ解くだけでなく、なぜその選択肢が正解(または不正解)なのか、理由をしっかり説明できるようになるまで繰り返し復習することが重要です。理想をいえば、10年分を3回以上繰り返すと、知識が定着しやすくなるでしょう。
Q. 受験申し込み後に住所や氏名が変わった場合の手続きは?
A. 氏名、住所、送付先などに変更があった場合は、速やかに手続きが必要です。
不動産適正取引推進機構のウェブサイトにある「住所等変更届」をダウンロードし、必要事項を記入して郵送で届け出る必要があります。この手続きを怠ると、受験票や合格証書が届かないといったトラブルの原因になります。引越しや結婚などで情報に変更があった場合は、忘れずに手続きを済ませましょう。
まとめ:宅建試験合格に向けて、しっかり準備を始めよう
この記事では、2025年度(令和7年度)の宅建試験日をはじめ、申し込みから合格発表までの全スケジュール、そして試験の基本情報について詳しく解説しました。
宅建試験合格への道のりは、決して短くありません。しかし、ゴールまでの地図(スケジュール)をしっかり頭に入れておけば、安心して学習という旅を進めることができます。
この記事で全体像を把握できた今こそ、あなたの合格に向けたスタートラインです。さあ、2025年の合格を掴み取るために、今日から第一歩を踏み出しましょう!

![「資格」と「比較」をするメディア[シカクラ]](https://shikakura-x.com/wp/wp-content/themes/shikakura/dev/public/assets/images/common/text3.svg)











![[タグから記事をさがす]](https://shikakura-x.com/wp/wp-content/themes/shikakura/dev/public/assets/images/common/text_tag_search.svg)