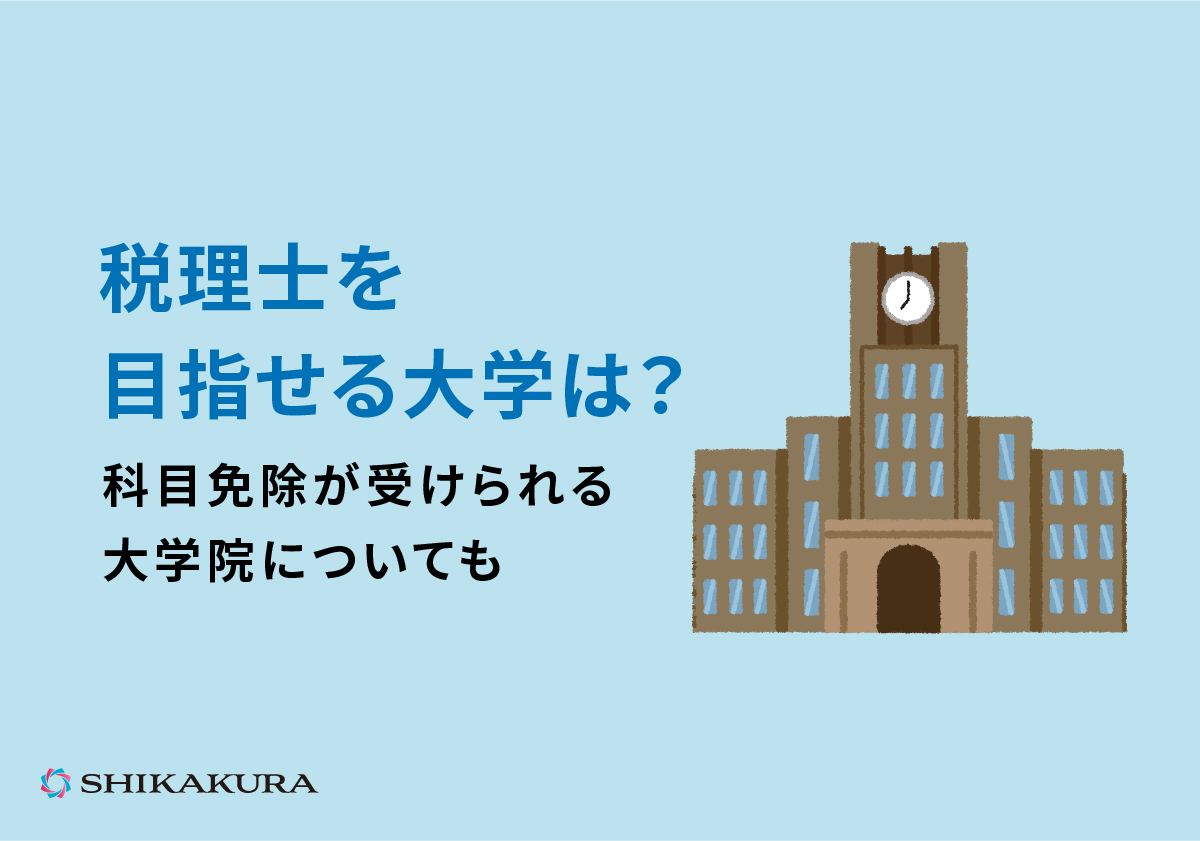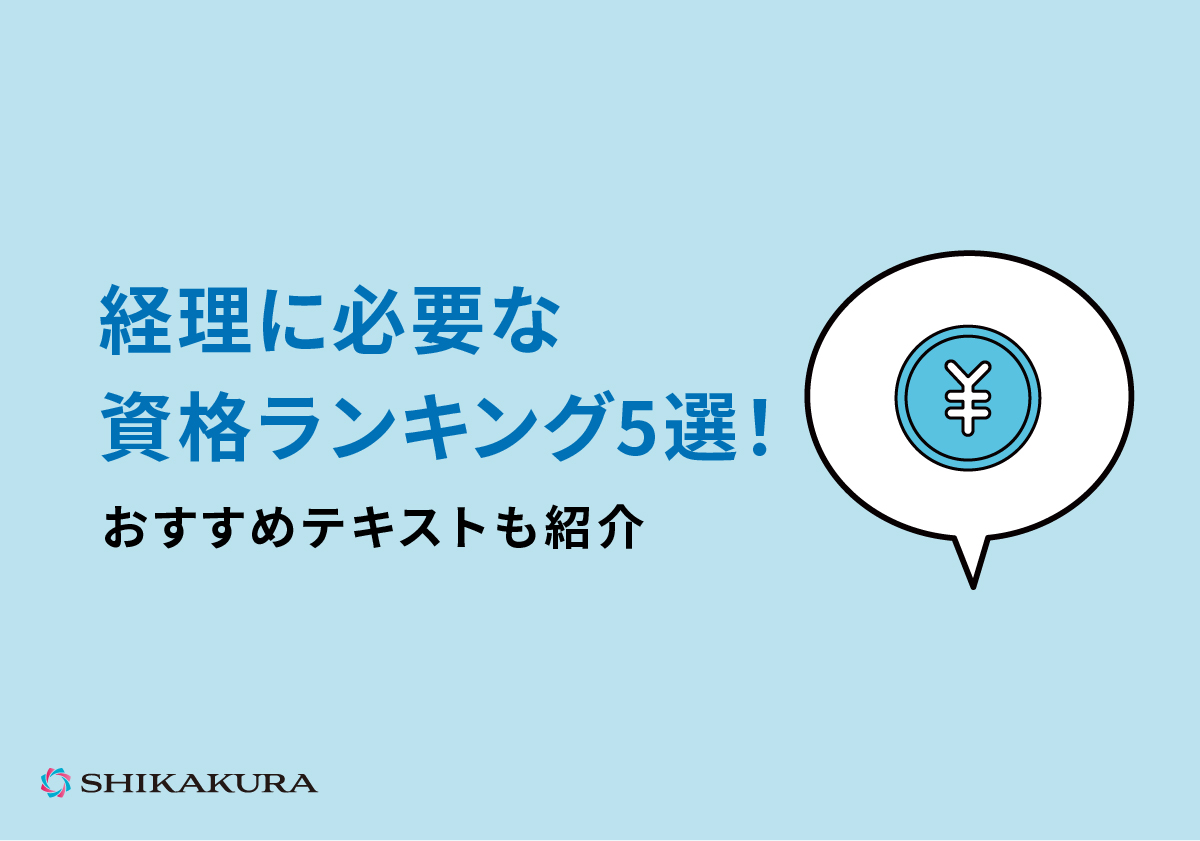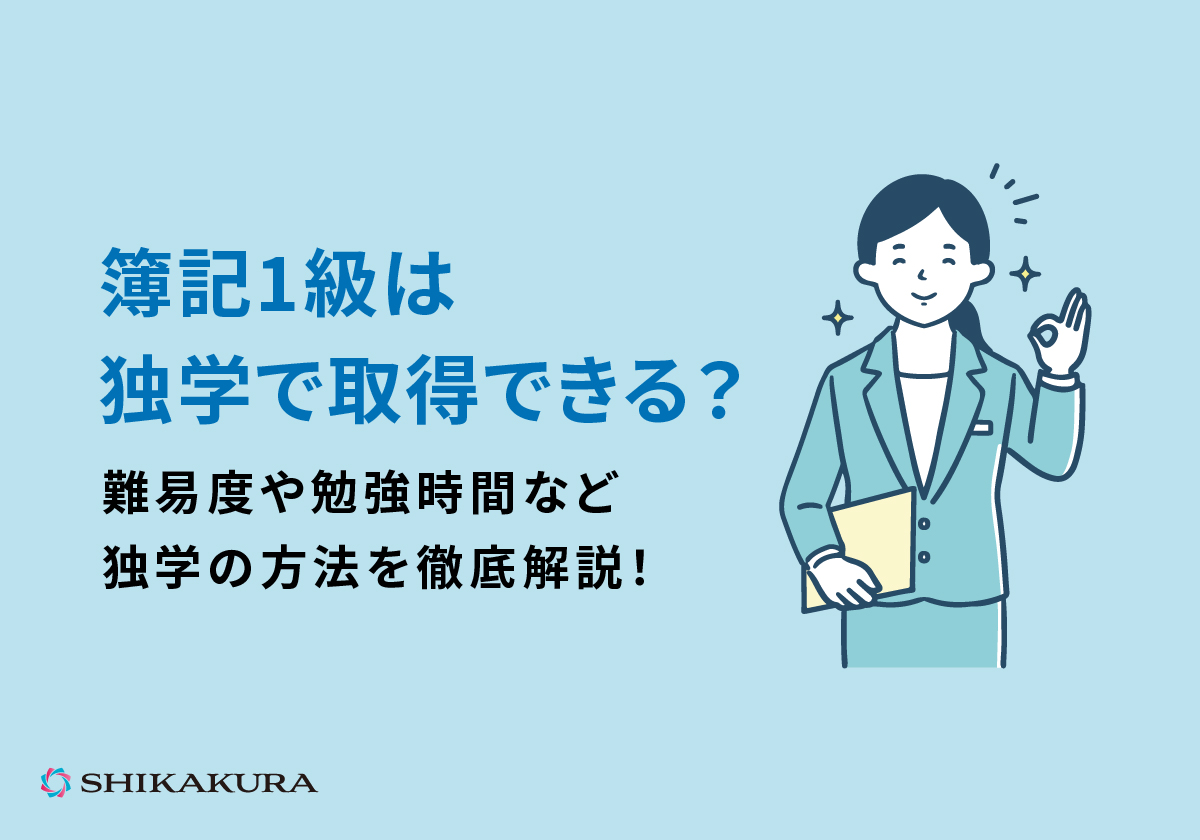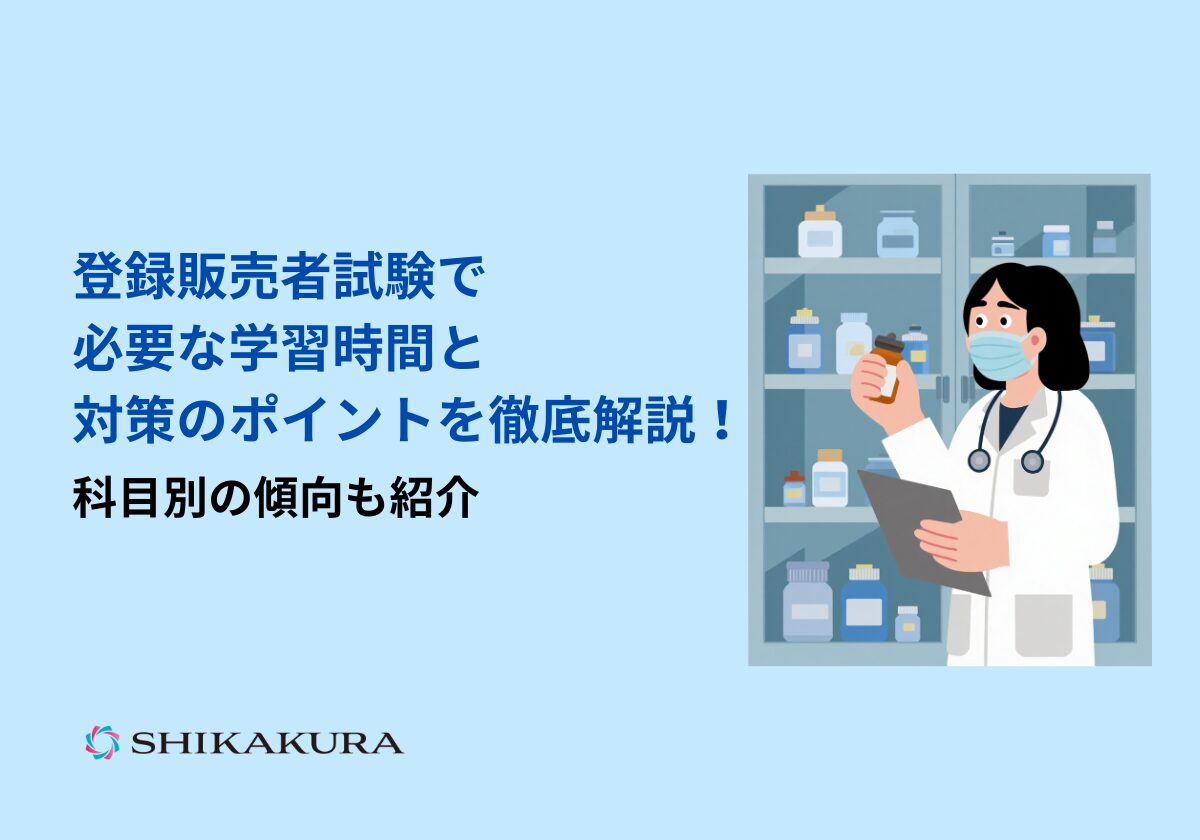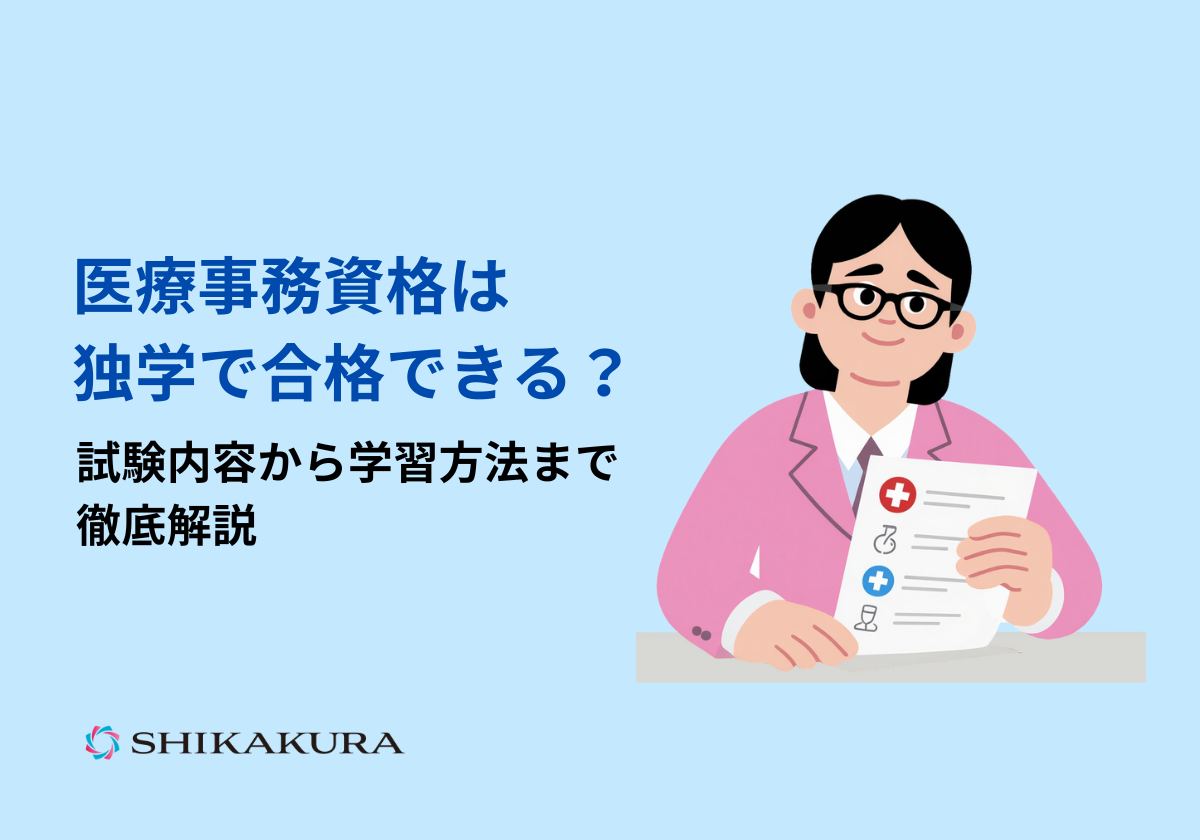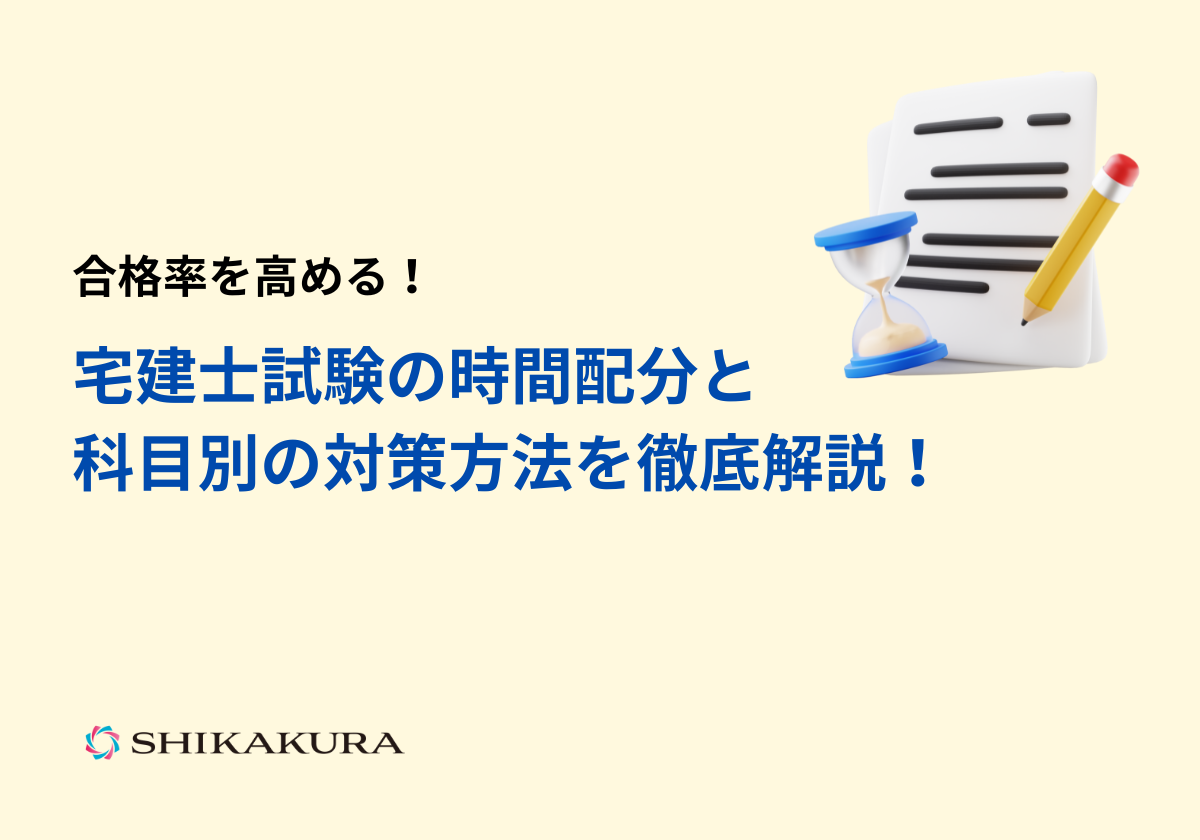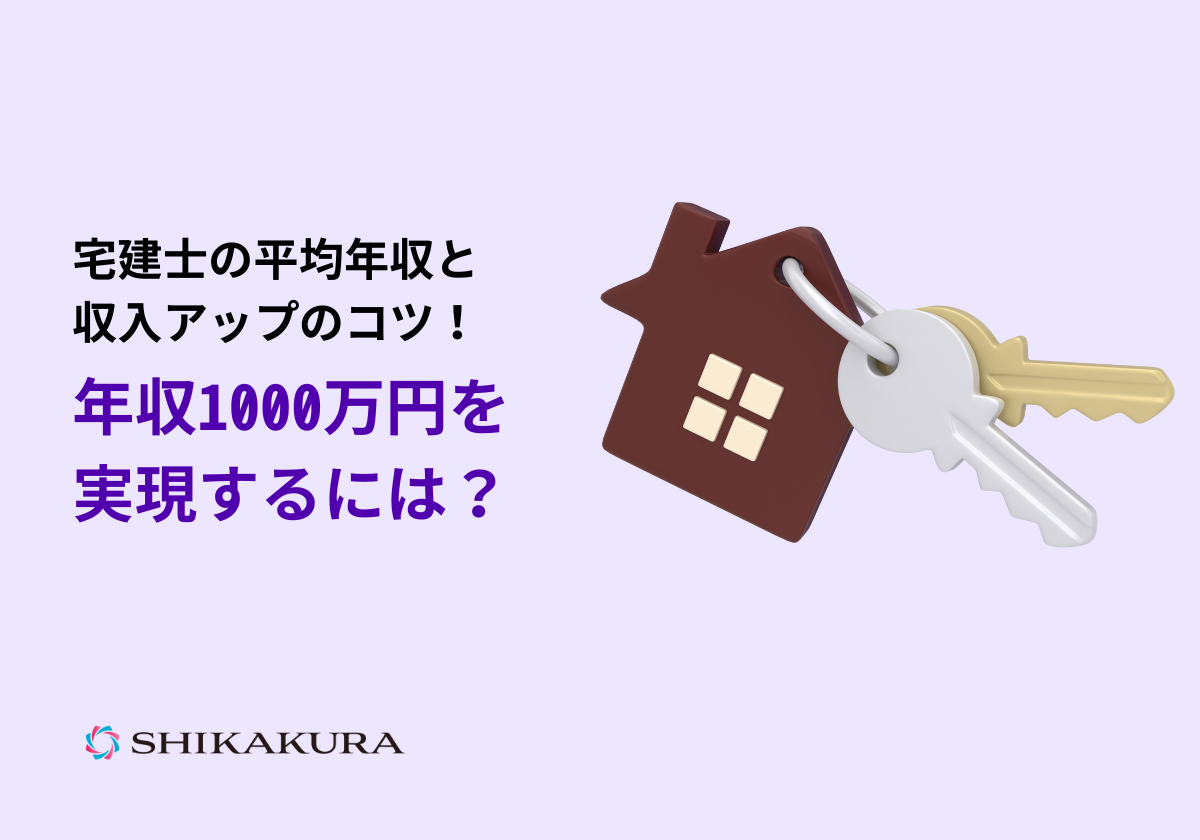公開:2023.3.1 更新:2025.9.10
公開:2023.3.1
公認会計士は独学で取得できる?合格率・難易度やおすすめの勉強方法を解説!
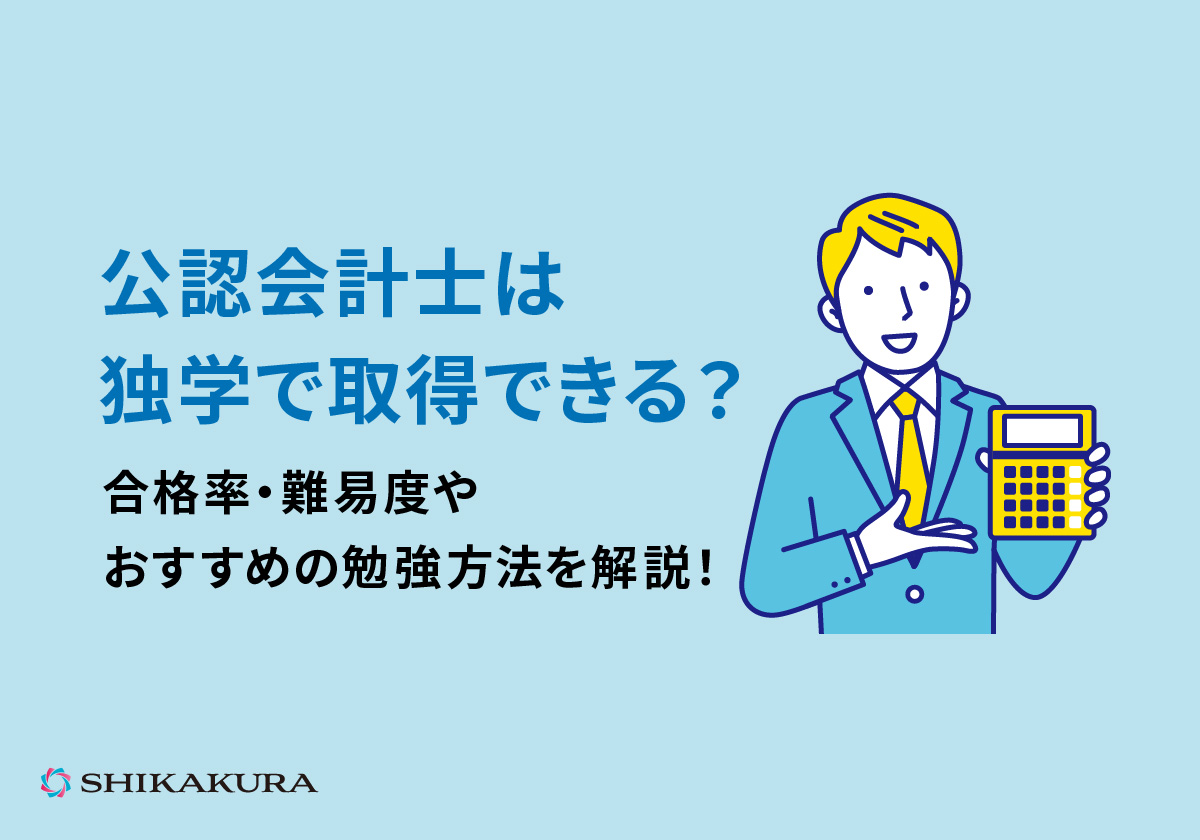
会計のプロフェッショナルといえる公認会計士は、計算能力と冷静な判断力が必要な仕事です。公認会計士になるには資格が必要になりますが、それは独学でも合格できるのか気になりますよね。
そこで今回は、公認会計士試験の難易度や勉強時間など、独学で合格を目指すためのポイントを紹介していきます。
目次
公認会計士試験とはどういうもの?
公認会計士試験は、財務会計・管理会計・監査・企業法など幅広い分野から出題される国家資格試験です。
公認会計士は高度な専門知識と論理的思考力が求められる職種です。試験に合格すれば会計・監査・コンサルなど幅広い分野で活躍できます。
公認会計士試験は独学で取れる?合格率は?
公認会計士試験の合格率
公認会計士の合格はハードルが高いものです。実際にどれくらいの人が合格をしているのでしょうか。
令和5年度の公認会計士試験では、願書提出者数20,317人のうち、最終合格者は1,544人で、合格率は約7.6%でした。
短答式試験の受験者は18,228人、そのうち合格者は2,103人。さらに短答式の免除者2,089人を加えた4,192人が論文式試験を受験しました。難易度が非常に高く、計画的な学習が求められる試験だということがわかります。
令和5年より前の合格率については、次の通りです。
| 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
| 願書提出者数(a) | 20,317人 | 18,789人 | 14,192人 | 13,231人 | 12,532人 |
| 短答式試験受験者数 | 18,228人 | 16,701人 | 12,260人 | 11,598人 | 10,563人 |
| 短答式試験合格者数(b) | 2,103人 | 1,979人 | 2,060人 | 1,861人 | 1,806人 |
| 短答式試験免除者数(c) | 2,089人 | 2,088人 | 1,932人 | 1,931人 | 1,986人 |
| 論文式試験受験者数(b+c) | 4,192人 | 4,067人 | 3,992人 | 3,719人 | 3,792人 |
| 最終合格者数(d) | 1,544人 | 1,456人 | 1,360人 | 1,335人 | 1,337人 |
| 最終合格率(d/a) | 7.6% | 7.7% | 9.6% | 10.1% | 10.7% |
出典:公認会計士・監査審査会より作成 https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html
公認会計士試験の独学の難易度
公認会計士試験は、合格までにおよそ2,500〜3,500時間の学習が必要とされる、非常に難易度の高い国家試験です。仮に1日5時間勉強した場合でも約1年半〜2年、1日3時間なら3年以上かかる計算になります。
試験科目は財務会計、管理会計、監査論など主要5科目に加え選択科目もあり、範囲が広く専門性も高いため、効率的な学習計画が求められます。
特に独学では、教材選びや優先順位の判断、最新の制度改正のキャッチアップも自力で行う必要があり、試験範囲の広さに加えて、適切な情報収集力が求められる点が、この試験の難易度をさらに上げる要因となっています。
公認会計士を独学で目指すメリット
公認会計士を独学で目指すメリットについて紹介します。
自分のペースで勉強できる
独学の最大の魅力は、自分のライフスタイルや理解度に合わせて、自由に学習を進められることです。
時間や場所に縛られず、好きなタイミングで勉強できるため、仕事や学校と両立したい方でも進められるでしょう。苦手な科目にはじっくり時間をかけ、得意な分野はテンポよく進めるなど、効率的かつ柔軟な学習が可能になります。
かかる費用を抑えられる
次に、かかる費用を抑えられる点です。
専門学校や通信講座を利用すると数十万円かかることもありますが、独学なら市販のテキストや問題集の購入費のみで済みます。経済的な負担を減らしながら資格取得を目指せるため、費用面がネックな方にとっては大きなメリットです。
自分に合った教材や勉強法を選択できる
独学では、数ある教材の中から自分に合ったものを選び、自分なりの学習スタイルを確立できます。インプット中心の学習が得意な人もいれば、問題演習で理解を深める人もいます。自由度の高い学習ができる点も独学の利点です。
独学のデメリットも知っておこう
公認会計士を独学で目指すにはデメリットも知っておかなくてはいけません。
環境を整えるのにお金がかかる
独学の場合、予備校ほどの金額ではありませんが、それでもテキストや参考書を購入したり勉強する環境を整えたりするには、それなりの費用が掛かります。また、公認会計士試験は合格率が低く、すべての科目に合格するまで数年かかることもめずらしくありません。そのため、法改正があった場合、予備校であれば即時対応しますが、独学の場合、自分で情報収集をしなければなりません。
そのため、自分から情報をキャッチして、それに対応できるようにする必要があります。テキストを購入する際は、最新の法改正にも対応している予備校のものを使用すると良いでしょう。
モチベーションの維持が難しい
独学は自分ひとりで勉強を続けるため、どうしてもモチベーションの波に左右されがちです。
公認会計士試験の勉強は長期間に及ぶため、勉強スケジュールを自分で組み立て、計画的に進める必要があります。周囲に同じ目標を持つ仲間や講師がいない分、学習への意欲を保つには工夫が必要です。目標の可視化や学習記録をつけるなど、自分なりの継続法を確立することが大切です。
疑問点の解消に時間がかかる
独学では、学習中に出てくる疑問点を自力で調べる必要があります。
検索や書籍で解決できることもありますが、正しい情報を見つけるまでに時間がかかることも少なくありません。特に専門性の高い論点では、誤った理解のまま進んでしまうリスクもあるため、情報の信頼性を見極める力が求められます。
公認会計士試験に向けて専門学校や通信講座を利用するメリット
独学以外で公認会計士試験の勉強をする方法は、主に2つあります。
1つは「専門学校や受験予備校へ通う方法」、もう1つは「通信講座を利用する方法」です。
下記にそれぞれメリットを紹介しますので、ぜひご覧ください。
専門学校・受験予備校のメリット
専門学校や予備校は知識のない人でも短期間で合格に近づけるように、カリキュラムが組まれています。また、分からないところがあれば、直接講師に質問をでき、その場で解消できるのもメリットと言えます。同じく合格を目指している人が周りにたくさんいるので、モチベーションアップにもなります。
通信講座のメリット
通学と同じようなサービスを受けられ、費用は通学よりも抑えられるのがメリットです。ライブ講義やオンライン配信されていることも多く、電話・対面での質問ができる通信講座もあります。勉強する環境が自由なため、合間に気分転換して、効率的に勉強がすすめられます。
公認会計士試験の勉強方法
公認会計士試験の試験内容
公認会計士の資格を取得するには、短答式試験と論文式試験の2種類の試験に合格する必要があります。
短答式試験は、毎年5月と12月に実施され、「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4つの科目となり、一度短答試験に合格すると、その後2年間短答式試験は免除されます。
一方、論文式試験は、8月に実施されます。「会計学(財務会計論・管理会計論)」「監査論」「企業法」「租税法」に加えて、選択科目(経営学・経済学・民法・統計学)から1科目受験します。論文式試験で不合格となった場合でも、一部の科目で相当の成績が得られれば、申請することで2年間は、該当する科目が免除されます。
公認会計士試験のおすすめの勉強方法
公認会計士試験に合格するためには、長期的かつ計画的な学習が不可欠です。
まずは全体像をつかむために、テキストで基礎知識をしっかりインプットしましょう。
その後は、過去問や問題集を繰り返し解くことで、実践的な力を養うことが重要です。短答式と論文式では出題傾向が異なるため、それぞれに適した対策が必要です。
また、学習記録をつけたり、定期的に模試を受けたりすることで、理解度の確認やモチベーション維持にもつながります。独学でも成功する人は多いですが、迷ったときは予備校の無料体験やオンライン講座を活用するのもおすすめです。
公認会計士を独学で目指す3つのポイント
公認会計士を独学で目指すうえでの必要なポイントをしっかりとおさえておくことで、途中で挫折することなく、勉強を継続しやすくなります。
ポイント1:スケジュールの管理
公認会計士の試験は試験範囲が膨大です。スケジュール管理が大切ですが、きちんとスケジュールを組んでしまうと、イレギュラーなことが起こった時、スケジュールを組みなおさなければいけなくなります。また、毎日勉強時間を詰め込みすぎると、無理が出てきてしまい、モチベーションが下がってしまうことにもなりかねません。特に社会人の場合は、毎日の仕事と並行して受験勉強をしなければいけないので、無理なスケジュールを組んでしまうと、仕事にも支障が出てしまいます。そうならないように余裕を持ったスケジュールで、時には休息の時間を入れるようにしましょう。
ポイント2:情報収集やコミュニティへの参加
公認会計士試験では法改正が行われると法令や制度が変更するたびに内容が大きく変わる可能性があります。
予備校であれば、講師が情報を常にキャッチして生徒にすぐ共有することもできますが、独学ではそういったサポートが受けられません。自分で情報を集める必要があるので、常にアンテナを張って情報をキャッチするようにしましょう。また、同じ目標をもった勉強コミュニティに参加すれば、そのような情報もいち早く流れてくるので、積極的に参加するといいでしょう。
ポイント3:答案練習会への参加
公認会計士の試験には答案練習会と呼ばれる、本番さながらの雰囲気で試験を受ける機会があります。練習会に参加すると、試験の雰囲気に慣れることができ、本番も落ち着いて試験が受けられます。練習会では実際の試験と同じ形式で出題され、試験によく出る範囲が出題されるので、本番で出る問題の予想ができ、広い範囲でも効率よく勉強に取り組めます。
答案練習会は予備校などでも実施しているので、積極的にスケジュールに組み込んでいきましょう。
公認会計士試験に合格したその後は?
試験に合格後、正式に公認会計士になるには、試験に合格したあと、3年以上の実務経験と実務補習が必要です。そのために、合格者の多くは、合格後すぐ監査法人への就職活動が必要になります。
合格前に就職準備をしておこう
公認会計士の論文式試験の合格発表は11月中旬に行われます。監査法人の定期採用は試験の合格発表が終り次第、一斉に始まって面接や書類選考をし、約2週間後には内定が出ます。そのため、合格後から活動を始めるのでは遅く、合格発表前に説明会に参加するなどして、情報を集めて面接の準備をしておきましょう。
まとめ
公認会計士の試験は合格率が低く難しい試験なので、計画的にスケジュールを組んで試験に挑む必要があります。さまざまなコミュニティに参加したり、気分転換をしたりするなどして、モチベーションを維持し、就職する時の準備も怠らないようにしましょう。

![「資格」と「比較」をするメディア[シカクラ]](https://shikakura-x.com/wp/wp-content/themes/shikakura/dev/public/assets/images/common/text3.svg)











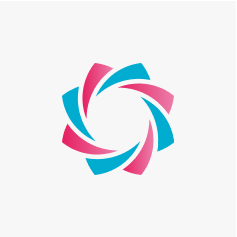
![[タグから記事をさがす]](https://shikakura-x.com/wp/wp-content/themes/shikakura/dev/public/assets/images/common/text_tag_search.svg)